“複業”のカフェ運営で「やってみる」価値を実感した彼女が、高校生に届けたいものとは/NEWFACE
 Interview
Interview
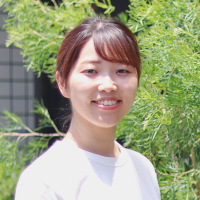
大塚 莉紗 Risa Ohtsuka 全国高校生マイプロジェクト
東京都出身、慶應義塾大学卒業。卒業後は自分の可能性を広げられる環境を求め、ユニークな事業・組織運営を行う決済会社に入社。顧客の導入支援~稼働後の伴走、顧客ニーズを反映したプロダクトや運用改善に向けた体制構築などを経験。2024年よりカタリバ入社。現在は全国高校生マイプロジェクトに所属し、「マイプロジェクトアワード」の企画・運営に携わる。
ここ10年で、仕事のあり方・捉え方は、まったく違ったものになってきている。終身雇用は崩壊、転職は当たり前のものとなり、複業やフリーランスも一般化。テクノロジーの発達によって無くなる仕事予想も大きな話題となった。給料や肩書よりもやりがいや意味を重視する若者も増え、都会から地方にUIターンすることも珍しくなくなった。世界が一斉に経験したコロナ禍をへて、今後ますます働き方は多様に変化していくだろう。
そんな中カタリバには、元教員・ビジネスセクターからの転職・元公務員・元デザイナーなど、多様なバックグラウンドを持った人材が就職してきており、最近は複業としてカタリバを選ぶ人材もいる。その多くは20代・30代。彼らはなぜ、人生の大きな決断で、いまNPOを、いまカタリバを選んだのか?
連載「New Face」では、カタリバで働くことを選んだスタッフから、その選択の背景を探る。
高校生が身近な課題や関心をテーマにプロジェクトを立ち上げ、実際にアクションをすることを通じて学んでいく「全国高校生マイプロジェクト」。その運営や仕組みづくりに携わっているのが、2024年7月に入職した大塚莉紗(おおつか・りさ)だ。
教育とは異なる領域の企業に勤務する中で、「行動してみること」の大切さを実感し、学びに関わる道を選んだという。カタリバに至るまでのキャリアと、現在の思いを聞いた。
「それが当たり前だから大学へ行く」だった高校時代

——現在「全国高校生マイプロジェクト」を担当されていますが、ご自身の高校時代の経験や価値観はどのようなものでしたか?
私は中高一貫校に通っていたのですが、当時そこでのキャリアに対する考え方として、「大学に進学するのが当たり前」「できるだけ偏差値の高い大学を目指すべき」といった空気を感じていました。その中で、私も自然と大学進学が当然と考えていたと思います。
でも、大学でいろいろな背景をもつ同級生や、寄り道を経て自分らしさを見つけてきた人たちと出会う中で、「私は中高時代にどんな選択をしてきたんだっけ?」と改めて自分に問い直すようになりました。
振り返ってみると、「大学で何を学びたいか」については考えていましたが、「そもそもなぜ大学にいくのか」といった問いを持たずに進んできたことに気づいたんです。高校時代にもっと多様な選択肢があると知った上で、自分がしたいことは何かと考えていたら、いろいろな可能性があったかもしれないと今は思います。
——卒業後の就職については、どのように考えていたのでしょう?
就活の時点では、これがやりたいというものが明確にあるわけではありませんでした。いろいろな企業に話を聞く中で、自分が納得してサービスをお客さんに届け、お客さんと一緒に価値をつくっていけるような仕事がしたいと思うようになったんです。
そうして出会ったのが、決済サービスを手がけるネットプロテクションズでした。
面接で「どんな価値観を大切にしているか」と問いかけられ、自分の内面に立ち返る機会がありました。価値観を尊重しながら挑戦できるこの会社なら、自分らしく働けそうだと感じ、入社を決めました。
社内には、新人の提案でもしっかり受け止めてくれる風土があり、考え抜いたアイデアは実際にプロジェクトとして動き出すこともありました。そうした環境の中で小さな一歩を積み重ねることで、少しずつ自信が育っていったように思います。
中高生向けインターンシップに伴走して受けた衝撃

——前職ではどのような業務をされていたのでしょう?
カスタマーサクセスとして、スムーズにサービスを導入・運用してもらうための仕組みをつくり、導入後の支援を行う業務を担当しました。
お客様から「このやり方で進めたい」と言われたときは、まずその背景にある「こうなりたい」という理想や課題意識について認識を合わせることを大事にしていました。そういう視点で考えると、そこにたどり着くのに最適な手段は、実は別のサービスや方法にあるかもしれない。
そんなふうに、ただ要求に応えるだけではなく、その奥にある意図やニーズに立ち返って提案するということが多い仕事でした。「お客様が本当に求めているものは何か」という視点をもつということを教えてもらった職場でした。
——入社3年目のときに中高生向けのインターンシップに携わったそうですね。
はい。5日間にわたる「次世代リーダー成長支援プログラム」という、中高生が参加するインターンシップでした。私はバディとしてチームに加わり、限られた時間の中でどれだけ濃い学びの機会を届けられるかを意識して伴走しました。
プログラム序盤は迷いがあり、「もっとこうできたのでは」と反省ばかり。でも、運営スタッフが「ここは良かったよ」「次はこうしたら?」と助言してくれたことで、関わり方を日々見直すことができました。
最終日には子どもたちの表情が本当にキラキラしていて、「やって良かった」と心から思えました。この経験を現場に持ち帰りたい、自分の人生にもつなげていきたいと感じました。
中高生の成長を支える場でありながら、関わる大人自身も育っていける。そんな場に立ち会えたことは、とても大きなインパクトになりました。
——その後、カフェの営業もされていたとか?
そうなんです。1年間、“複業”としてカフェ運営をしました。場所は間借りで、月1回から始め、週1回ペースで開店していたことも。仕込みから接客、調理、片付けまで、すべてひとりで担うスタイルでした。
周囲の友人からは「複業なんてすごいね」「私にはとても無理」という感想もありました。だけど、自分にも、そして誰にでも小さくてもチャレンジしてみることで、力を発揮できる場面はあるはずだと思うんです。
それは中高生インターンシップの伴走でも感じたことです。そのままの自分でも認められるゾーンから、チャレンジゾーンに一歩踏み出したことで、子どもたちはキラキラした笑顔になりました。ためらいやハードルがあっても、自分の考えを行動に移すことで、大きな変化が起こると思うんです。
——そんな複業での気づきもあって、次のステップに進む決断をされたのですね。
変われるきっかけを多くの人に、特に子どもたちに届けられれば。そう思うようになりました。
ちょうど仕事のチーム体制も安定してきていたところで、自分の仕事を他の人に安心して任せることができる状態でした。私も次の場所でチャレンジしてみよう――そんなふうに気持ちが固まったんです。
全国Summitに参加し「ここで働きたい」思いが決定的に

——カタリバとの出会いはどのようなものでしたか?
ある採用情報プラットフォームで、カタリバの採用担当の方から「全国高校生マイプロジェクト」の求人を提案されたんです。事業の概要を知るうちに、「自分が目指したい支援のあり方に近い」と感じました。特に「自分でやってみる」という体験を通して、気づきや学びにつなげていく場のつくり方に、強く共感しました。
そして面談の直後、マイプロジェクトの「全国Summit」を現地で見学する機会がありました。それが、私の中で「ここで働きたい」という思いを決定づけたように思います。
——実際に現地で見た全国Summitでは、どんなことが印象に残りましたか?
高校生たちが各々のテーマを発表するのですが、「発表して終わり」「参加したことが思い出になる」というものではないことに共感しました。発表の後に高校生たちが「この場で何を感じたか」「何を持ち帰るか」を言語化する時間が設けられていて、大人も同じチームとしてその時間に伴走していたんです。
 2025年全国Summitでの振り返りの時間の様子
2025年全国Summitでの振り返りの時間の様子
ただ発表するのではなく、自分の中に変化を起こす場としてデザインされている。それは、前職で私が中高生向けインターンに関わっていたときに大切にしていた価値観とも通じるものでした。この場づくりの一員になって、子どもたちを支えていきたい。そう強く思いました。
——その体験が、入職の決め手になったのですね。
その後の面談でも、カタリバのスタッフの方々と話す中で、組織として大切にしている価値観に一貫性があって、それが行動や仕組みにまでしっかり落とし込まれていると感じました。
ビジョンというのは掲げるだけでなく、「どう実現していくのか」という道筋に無理がないことが何より大事だと思っています。その点でも、カタリバには納得感がありました。
この場所でなら、自分がこれまで大切にしてきたことを活かしながら、新しい挑戦ができるかもしれない。そう思えたことが、入職の大きな後押しになりました。
より多様な高校生が参加できる開かれた場づくりにトライ

——あらためて「全国高校生マイプロジェクトアワード」とは、どのような場なのでしょうか?
自分の“好き”や“困りごと”からプロジェクトを立ち上げ、正解のない問いに向き合いながら、実際にアクションを起こす。そんな「マイプロジェクト」に取り組んできた高校生が集い、互いに学び合う場が「全国高校生マイプロジェクトアワード」です。
私はマイプロジェクトアワード全体の企画・設計・運営に携わっています。各地で開催される地域Summitが円滑に進むよう、運営パートナーの方々と連携しながら、必要な情報や資材を整理・提供するなどの対応をしています。
各Summitの裏では多くの人の思いや調整が重なり合っています。関わる高校生はもちろん、先生方や地域の方々、事務局スタッフまで、立場も視点も異なる関係者が集まる中で、「今、この人は何を大切にしているか」を想像しながら動くようにしています。
前職で培った視点が、今にもつながっていると実感しています。
——どのような点にやりがいを感じていますか?
高校生が自分の言葉で語り、表情をイキイキと変えていく姿を見ると、やっぱり「この仕事をしていて良かった」と思います。プロジェクトを通じてどんな気づきがあり、どう変化したのかが伝わってくる。それを現場で感じられることは、何よりのやりがいです。
また、同じ目的に向かって考え抜くチームで働けることも、励みになっています。「全国高校生マイプロジェクトアワード」の運営は「これが完成形」というものがなく、毎年「これまでのベスト」を更新しながらつくっています。
そうした文化がチーム全体に根づいていて、「今、何が必要か」をみんなで考え続けられる環境があることがうれしいです。
——マイプロジェクトを通じて、これからどんな価値を届けていきたいですか?
マイプロジェクトで大切なのは、強いモチベーションよりも、まず一歩を踏み出してみることにあります。何気なく参加した高校生が、プログラムを通じて変化していく姿を見てきました。このような機会が、高校時代のうちにあることが本当に大切だと思います。
これからはマイプロジェクトを、より多様な高校生が「自分も参加したい」と思えるような、開かれた場にしていきたい。マイプロジェクトが大切にしてきた“熱量”や“挑戦”という価値を守りながらも、その入り口をもっと広げていけるように。そうした仕組みや場づくりに、これからも丁寧に取り組んでいきたいです。
インタビューで印象に残ったのは、「自分のペースで、確かめながら進んでいきたい」という大塚の姿勢だった。「石橋を叩いて渡るタイプ」と自身を評しつつ、「どの橋を渡るかと同じくらい、誰と渡るかを大切にしている」とも語る。
取材当日は、ちょうど入職から1年。全国高校生マイプロジェクトを支えるその姿勢には、この1年で積み重ねてきた確かな歩みが感じられた。
関連記事
・「探究は自分の未来をつくる」高校生が挑んだ“長崎のアオリイカ”プロジェクト[マイプロジェクトアワード受賞者×伴走者インタビュー]
・記者からNPOへ転職。「社会を変えたい」という思いを胸にカタリバを選んだわけ/NEWFACE
カタリバで働くことに関心のある方はぜひ採用ページをご覧ください

佐々木 正孝 ライター
秋田県出身。児童マンガ誌などでライターとして活動を開始し、学年誌で取材、マンガ原作を手がける。2012年に編集プロダクションのキッズファクトリーを設立。サステナビリティ経営やネイチャーポジティブ、リジェネラティブについて取材・執筆を続けている。
このライターが書いた記事をもっと読む

